| 記事‐6 目 次 | |||
| NO | 記事年月日 | 記事元 | 見出し(記事内容) |
| 90 | 2003/3/25 | nikkei | 公示地価、下落率が拡大 |
| 89 | 2003/3/16 | 南日本 | 中国新体制 |
| 88 | 2003/3/17 | nikkei | 平均賃料低下、質の競争に |
| 87 | 2003/3/16 | nikkei | 資産下落と政策遅れ移す |
| 86 | 2003/3/12 | nikkei | インフレの足音 |
| 85 | 2003/3/2 | nikkei | 中国発 物価安 アジアに拡散 |
| 84 | 2003/3/1 | nikkei | 中国の経済成長は脅威か |
| 83 | 2003/2/13 | nikkei | 国債発行残 900兆円台に |
| 82 | 2003/2/12 | nikkei | 資産再生へのシナリオ |
| 81 | 2003/2/11 | 南日本 | デフレ懸念 世界に広がる |
| 80 | 2003/2/3 | nikkei | 都市集積が新産業育てる |
| 79 | 2003/1/31 | nikkei | 購買力 広州が最大 |
| 78 | 2003/1/17 | nikkei | 大型マンション首都圏に続々 |
| 77 | 2003/1/15 | nikkei | 起業収益に中国効果 |
| 76 | 2003/1/8 | 南日本 | ネットで競売物件公開 |
| 75 | 2002/12/29 | nikkei | デフレ克服 奇策なし |
| 74 | 2002/12/25 | 南日本 | 来年度予算 政府案決まる |
| 73 | 2002/12/21 | nikkei | アルゼンチン債 500億円債務不履行 |
| 72 | 2002/12/21 | nikkei | こうなる税制 ―6― |
| 71 | 2002/12/18 | nikkei | デフレが蝕む 私の見方② |
トップページ
.
| NO.90 | 2003/3/25(火) 日本経済新聞より |
公示地価、下落率が拡大 12年連続下落 住宅地5.8% 商業地8.0% 国土交通省が24日発表した今年1月1日時点の公示地価は全国平均で前年比6.4%下がり、12年連続で下落した。土地の需要は冷え込んだままで、下落率は2年連続で拡大した。東京都心部では再開発効果などにより下げ止まりや反転の動きも出てきたが、地方の平均下落率は6.0%とバブル崩壊後最悪を更新。資産デフレが加速し、企業や金融機関の大きな重しになっている。 全国平均で住宅地は5.8%、商業地は8.0%下落した。住宅地の下げ率が0.6%拡大した半面、商業地は0.3ポイント縮小。住宅地はピーク時の1991年に比べ39.7%下がり、ほぼ87年の水準。商業地は同65%下がりほぼ79年の水準にまで落ち込んだ。 東京、大阪、名古屋の三大都市圏では、住宅地は91年比で55.2%下落と半値以下、商業地は77.7%下落と4分の1以下になった。 地価が収益性や利便性など利用価値に応じて決まる動きが顕著になってきた。商業地は東京圏で4年連続して下落のテンポが鈍くなった。一方、人口10万人以上の地方都市の商業地下落率は10.5%。中心部の大型店撤退などが続き、下げ止まる兆しは見えない。 住宅地は東京都で横ばい、または上昇する地点が目立ち始めた。住宅需要の都心回帰が定着したことが主因。渋谷区が15年ぶりに上昇に転じ、大田区でも田園調布などで上昇地点が目立った。 |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.89 | 2003/3/16(日) 南日本新聞より |
中国新体制 20年にはGDP 4倍増 「世界の一極」目指す 胡錦濤国家主席の中国新体制が15日確立した。長期目標は「小康社会(いくらかゆとりのある社会)の全面的な建設」。表向きは日本の所得倍増計画に似た2020年までの国内総生産(GDP)4倍増計画だが、そこには米国に対抗しうる国力を備えて世界の一極に成長しようとの戦略的狙いが込められている。 中国筋によると、全国人民代表大会(全人代)の開幕直前、国家主席就任を間近に控えた胡氏は非公開会議で「現在の国際情勢は試練よりチャンスが多い。20年までが重要な戦略的チャンス」と強調した。 チャンスの一つは国際環境。今後十から二十年間、世界の多極化と経済のグローバル化が進展する。台湾問題を除けば、中国が戦争に巻き込まれる可能性は少なく、平和な国際環境を追求すれば経済建設に集中できるとの分析だ。 もう一つは国内の経済発展。このまま7%の経済成長を持続できれば10年にはGDPが二兆ドル、貿易額は一兆ドルに達し、世界の総額の5%を占めるまでになる。国家統計局は20年に日米に次いで総合経済力は世界三位になるとの試算もはじき出している。 清華大学国情研究センターの胡鞍鋼主任は20年までの発展方針を①経済成長②総合国力の増強③国民生活の向上④国際競争力の強化――の4点にまとめた。米国との国力の差を率直に認め足元を固める戦略。胡体制はこうした青写真に沿って、国内の安定と発展を目指す改革の道を全力で歩むだろう。 イラクや北朝鮮の問題に対して積極介入しないのも、外交より国内の大戦略を優先しているため。政治体制改革も安定を壊さない範囲内で経済発展に役立たせるための調整を進めることになろう。胡主席ら新指導部は、政治的混乱さえなければGDP4倍増の達成は十分可能とみている。 十九世紀末の洋務運動のチャンスを逃して日本に先を越され、二十世紀の米ソ冷戦も生かし切れずに文化大革命で世界から後退した。その歴史的失敗を教訓として中国は超大国の米国に挑もうとしている。 (北京、共同=中川潔) |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.88 | 2003/3/17(月) 日本経済新聞より |
《月曜経済観測》 東京でビル大量供給 平均賃料低下、質の競争に 三菱地所社長 高木茂氏 デフレが長引く中で、地価の一段の下落を懸念する声が強まっている。都心部で大型ビルが相次いで完成するうえ、株価不安が追い討ちをかけるためだ。一方で都市再開発には経済波及効果も見込める。不動産から見た景気の先行きを三菱地所の高木茂社長に聞いた。 集客で消費刺激 ――東京でビルが大量供給される「2003年問題」は、景気にどんな影響を与えますか。 「空室率が上がると指摘されるが、都心部の再開発は経済全体への波及効果も大きい。住宅建設が活発になると家電製品などの売れ行きが良くなるのと似ている。オフィスビルでは建設、素材、情報技術関連産業などの需要創出が期待できる」「小売店やレストランの集客効果で消費も刺激する。当社の丸ビル(千代田区丸の内)ではテナントが半年に170億円を売り上げ、初年度の予想をほぼ達成した。デフレでタンス預金をしていた人が、財布のひもを緩めてくれたようだ」 ――東京駅周辺では来年以降も再開発が続きますが、その効果は。 「大手町・丸の内・有楽町地区では16のプロジェクトが予定されており、当社も含めて民間企業が計8000億円の投資を計画している。野村総合研究所の試算では一兆九千億円の波及効果があり、十三万人弱の雇用を吸収するという」 ――ただ、テナントの誘致合戦も激化します。周辺の既存ビル需要の落ち込みも深刻では? 「間違いなく質の競争になる。今後は隣同士のビルでも、情報化対応など付加価値によって賃料や地価の格差が広がる。平均値では語れない。合理的な価格形成になってきたといえる。」「しかし、市場全体を見れば景気低迷の影響を免れない。昨年は米同時テロとデフレの影響でテナント需要が落ち込み、都区内で9年ぶりにオフィスの利用床面積が減った。今後も平均値としてのビル空室率は上昇し、賃料相場は下落するだろう」 ――株安は地価に響きますか。 「株式市場では銀行と企業の持合い解消という売り圧力があるうえ、イラク、北朝鮮といった地政学的リスクが重なっている。地価も株価に連動する傾向があり、逆資産効果が強まって消費が冷え込みかねない」 ――銀行の不良債権問題への影響は。 「銀行が不良債権処理のために担保不動産を売却すれば、地価を押し下げる要因になる。地価が下げとまらないと、担保不足となって、また不良債権が増えてしまう」 地価の下落続く ――全国全用途平均の公示地価は昨年まで11年連続で下がっています。反発は見込めますか。 「(近く発表される)今年1月時点の公示地価でも下落傾向は続いているだろう。地方都市の商業地は低迷が続いている。マンションも都心や超高層の物件は以前人気を集めているが、全体としては多少、売れ行きが鈍ってきた。全国平均の地価は日本経済を反映するのだから、デフレが止まらない限り反転のめどは立たない」 ――デフレ脱却にどんな対策が必要ですか。 「不良債権処理は重要だが、それだけではデフレを止められない。需要創出策が欠かせず、都市再生などの公共投資が有効。我田引水といわれると困るが、要は客観的に見て乗数効果の高い案件に絞り込むことだ」「官民に共通する課題として、海外から企業や資本、観光客を呼び込むことも大切だ。例えば海外からの旅行者数を見るとフランスは年間7000万人を超えているのに、日本は400万人台。都市基盤や観光資源の蓄積はあるのだから、もっとピーアールをしてアジアでの日本の存在感を高める必要がある。」 (聞き手は編集委員 塩田宏幸) |
|
目次へ戻る
.
| NO.87 | 2003/3/16(日) 日本経済新聞より |
資産下落と政策遅れ移す デフレ深刻 「不安」が増幅 デフレ論議がたけなわだ。物価の継続的(二年以上)な下落をデフレーションという。小泉純一郎首相は、福井俊彦次期日銀総裁に「デフレ退治」を託す形だが、人事内定後の市場は、イラク戦争への緊迫感もあって、円高、株安、債権高が加速している。 市場の反応は超低金利の継続を意味する。「デフレ対策は続くがデフレ脱却はできない」との読みだ。デフレ脱却で長期金利が上昇すると、財務省の国債消化に都合が悪いし、日銀も総資産の約半分を占める国債の含み損拡大を避けたいのではとの見方である。 そこで、「デフレと対決する『建前』より、デフレとの共存が『本音』ではないか」(英エコノミスト誌)と皮肉る声も出る。確かにデフレの言葉は踊るが、過去の政府・日銀によるデフレ対策の効果は小さい。議論と対策でギャップが生じるのは、デフレが及ぼす影響の程度を十分つかめていないためではないか。 消費者物価指数と企業物価指数(旧卸売物価指数)は共に1998年から4年連続で伸び率はマイナス。国内総生産(GDP)デフレーターも同様で、消費税引き上げの97年を除けば、94年から下落中。紛れもない長期デフレだ。 直近の下落率は一月の消費者物価が前年同月比0.8%、二月の企業物価は0.9%と小幅。だらだらと下がり続ける具合だ。内外価格差が残ることから、「価格が下がるのは望ましい」との「良いデフレ論」もいまだある。だが、企業活動には先行き不安がにじみ出る。クレディ・スイス・ファースト・ボストン(CSFB)証券が企業の感じる期待インフレ率を試算したところ、直近でマイナス3.65%。一般物価の下落率を4倍も上回る水準という。 消費者はどうか。内閣府が国民生活モニターに今後一年間の物価見通しを定期的に聞く意識調査では、一時縮小していた「下がる」と「上がる」の差が12月には2ポイントに開いた。デフレ感が増す気配がある。 一般物価よりも企業や消費者のデフレ予感が高いのはなぜか。企業の場合、過剰設備を依然抱え、保有資産の価格下落懸念も大きい。大都市圏の商業地価は二ケタの下落が続き、株価の底も見えない。 ”期待デフレ”の大きさは、企業の金利負担感の増大をもたらす。名目長期金利から期待インフレ率を引いた期待実質金利は5.7%のも及び、今もバブル期並み。さすがにこの「高金利」では新規事業意欲はわかない。加えてデフレ無策の政府・日銀への不信感は深まる一方だ。 「ゆでガエル」論を思い出してほしい。熱湯にカエルを入れると飛び出すが、冷たい水に入れ、ゆっくり温度を上げるとカエルは気づかず、ゆで上がる話。一般物価の下落が緩やかだからと言って、無策を続けていると、日本経済はゆで上がりの逆で、凍りつく。 日銀はバブル期に一般物価の安定に目をとられ、資産バブルの膨張を見逃した。目下の資産デフレと期待デフレの大きさを見逃せば、反省もなく失敗を繰り返すことになりかねない。 (編集委員 藤井良広) |
|
目次へ戻る。
.
| NO.86 | 2003/3/12(水) 日本経済新聞より |
「大機小機」 インフレの足音 デフレ克服に向けてあらゆる手段の総動員を求める世論が高まる中で、第29代日銀総裁に福井俊彦氏が近く就任する。新体制の下で政府・日銀一体の強力なデフレ退治が始まろうとしている。 だが、物価動向を眺めると既に素材価格中心に値上がりが始まっており、デフレに代わってインフレが芽生えていることを見落としてはいないだろうか。 確かに、中国製品の安値攻勢と不良債権問題を抱え、デフレは当分続かざるをえないように見える。だが、中国は世界の工場であると同時に巨大な消費市場でもある。また、不良債権処理と同時に、潤沢な資金が実物投資に向かっている。イラク攻撃後の国際紛争の拡散も心配だ。デフレ要因だけに目を奪われていると大局を見誤る可能性がある。 事実、世界貿易機関(WTO)加盟を契機に中国の輸入が急増して世界の商品需給をひっ迫させ、国際商品価格の高騰に拍車をかけている。国際商品価格の上昇は輸出入価格を通して国内物価に波及し始めた。 2年前のゼロ金利復帰と異例の量的緩和政策の影響も見逃せない。日銀による資金大量放出でマネタリーベース(現金と日銀当座預金の合計)は2年間で65兆円から93兆円に膨張した。未曾有の金融緩和で行き場を失った資金が国債市場からあふれ、商品価格を押し上げ始めた。 国内商品価格動向を示す代表指標である日経商品指数42種は一昨年末反騰に転じ、ほぼ全面高となっている。従来の卸売物価指数に代わる企業物価指数にも値上げの連鎖が見られる。素材や原材料価格に続いて昨年8月から輸出入価格が上昇し、10月には中間財価格が下げ止まり、最終財価格の一部に素材価格の値上げが浸透し始めた。消費者物価にも下げ止まりが見られる。 前代未聞のマイナス金利が出現し、インフレの足音が聞こえる中で政府・日銀が一体となり力いっぱいアクセルを踏んだらどうなるか。かつて円高不況におびえ超低金利政策を続けた結果バブルを起こし、逆にバブル退治の強力な引き締め政策が平成デフレを招いたように、極端な金融政策の先には思わぬ落とし穴が待ち受けているものである。デフレはいつまでも続かない。デフレが終わったとき新しい波が始まりお金の流れは一変する。そろそろ準備が必要かもしれない。(富民) |
|
目次へ戻る
.
| NO.85 | 2003/3/2〔日〕 日本経済新聞より |
「デフレが蝕む」 中国発 物価安 アジアに拡散 香港 不動産・賃金を直撃 グローバル化で加速 デフレがアジア各地に広がっている。内閣府の調査によると、2002年の消費者物価は香港で前年比3%の大幅低下となるなど、主要な国・地域で下落が目立つ。中国経済の台頭で低価格の製品が流入する一方、生産拠点の中国シフトがアジア企業にも浸透し、賃金や不動産価格の低下を招いている。経済のグローバル化で物価下落が続く、構造的なデフレがアジアで加速する可能性もある。 2002年の消費者物価で下落率が最も大きかった香港は、日本と同じく4年連続のマイナス。香港のデフレは中国本土との経済の一体化が背景にある。「経済の壁」がなくなり、モノや労働力が自由に出入りするようになったためだ。 香港では隣接する中国・深しんとの間の高速道路が今年1月末から24時間通行できるようになった。深しんにマンションを購入して香港に通勤する人や、物価の安い中国本土に買い物に出かける香港市民が急増中だ。 中国本土側へ境界を超えるだけで不動産価格は半値から3分の一。マッサージや散髪などサービス需要も中国本土に流出し、企業の売り上げ高の目減りだけでなく、所得減少や失業率の上昇を招いている。中国との価格の平準化が強烈なデフレ圧力をもたらしている。 シンガポールの昨年の消費者物価は前年より0.4%下落し、4年ぶりのマイナス。台湾も0.2%下落した。中国製の割安な衣料品や日用品などが流れ込んでいる。台湾では情報技術(IT)関連の生産拠点が中国に移転しており、産業の空洞化が進んでいる。 香港に比較してシンガポールや台湾のデフレの影響は今のところ限定的だが、中国の世界貿易機関(WTO)加盟などで「より安い価格への修練」は避けられなくなっている。 みずほ総合研究所の中島厚志チーフエコノミストは「中国の市場経済化で特にアジアでは価格の均衡が進んでいる」と指摘。安価な製品流入の一方、工場流出で結果的にコストの低い労働力が輸入されたのと同じ効果が表れている。 アジアでも、インドネシアやマレーシアでは明確な物価の下落傾向は出ていない。地理的に中国から遠いだけでなく、日本やシンガポール、台湾に比べ製品輸入や企業の海外進出が多くないためとみられる。貿易や投資自由化などグローバル経済に深く組み込まれるほど、デフレが波及しやすい構造になっている。デフレの発信源とされる中国だが、自らも物価下落に直面している。昨年の消費者物価は0.8%の下落。月次の消費者物価は一月に上昇に転じたものの、投資ブームで過剰設備を抱え、供給超過になっている。 中国では携帯電話などの家電で値引き販売が激化。過当競争に陥った企業がシェア拡大のため価格を引き下げている。都市部では自動車や住宅への需要が強いが、供給力拡大のピッチを越えられるかどうかは微妙だ。 |
|
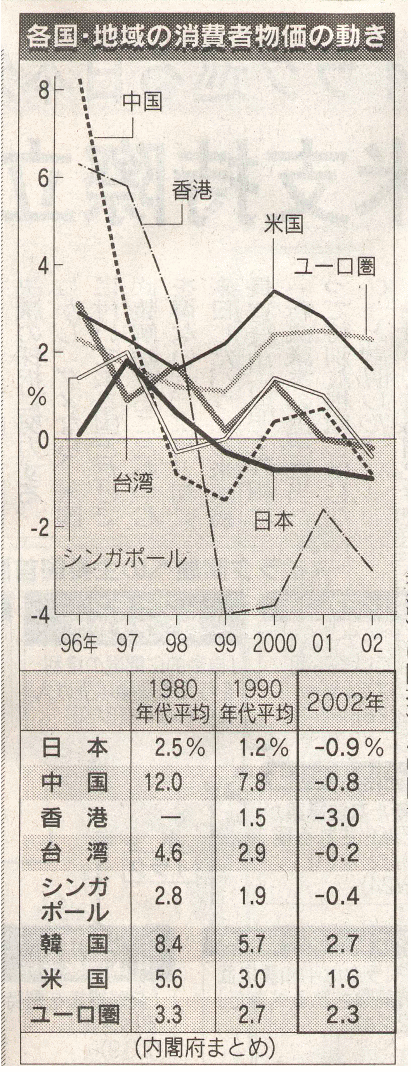 |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.84 | 2003/3/1(土) 日本経済新聞より |
「大機小機」 中国の経済成長は脅威か 中国の経済発展が、世界経済の勢力地図を一変させようとしているのは、盛んに報道されている通りだ。大量・安価な労働力に支えられた旺盛な製品輸出は、世界的なデフレ要因として、警戒の目が向けられている。さらには、靴から自動車まであらゆる組み立て産業の生産拠点の中国シフトは、東南アジア・中南米の中心国から、日本のような工業先進国までの広い経済圏に対して、産業空洞化、雇用の喪失をもたらしており、こうした国々での中国脅威論はさらに顕著だ。 しかし、冷静に統計データを見ると、違うシナリオも見えてくる。確かに、世界貿易の輸出シェアに占める中国の割合は、2001年度ベースで4.4%まで急成長しており、日本の6.6%を追い越すのは時間の問題である。既に、米国向け輸出額のシェアでは、2002年時点で中国は日本をわずかに抜いて、ナンバーワンになっている。 一方で、中国はアジア諸国における最大の輸入国になっている。日本をはじめとする近隣諸国から基幹部品などが中国に輸入され、現地で組み立てられた完成品が再び世界の市場に供給される構図だ。さらには、携帯電話や自動車のように、組み立て後に、中国国内市場で消費されていく商品も多い。 つまり、中国は世界の工場の地位を固めつつある一方で、アジアの輸入大国にもなってきているのだ。さらにこの先、消費大国へ進化することで、世界経済のけん引車となる、という希望シナリオも描けるのである。むしろ、中国経済が失速してしまうことによって、世界経済が被るダメージの方がはるかに深刻であることを認識すべきだ。 日本は、こうした中国の希望シナリオを積極的に受け入れると共に、そのメリットを享受するための自らの改革を推し進めなけれいけない。企業は、部品や素材レベルにおける高度技術、斬新なビジネスモデル、魅力的な商品デザインやブランド力、そして、卓越した経営管理力など、いわゆる無形資産を核に据えた事業展開を行うことが、対中国戦略の鍵となる。加えて、政府は、構造改革の推進により、サービス産業の革新を図り、経済の内需拡大を実現することが不可欠だ。 安易な中国脅威論に流れずに、世界経済の転換点にいることを認識して、国家も企業も戦略を再構築し、改革を断行するときなのだ。(六本木族) |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.83 | 2003/2/13(木) 日本経済新聞より |
国債発行残 900兆円台に 2016年度末 財務省試算 財務省がまとめた今後の財政状況に関する試算によると、13年後の2016年度末の国債発行残高は900兆円前後と来年度末段階の450兆5千億円から倍増する。 04年度以降の実質経済成長率を0.5%と仮定した場合の試算では、国債の発行残高は16年度末に929兆8千5百億円と900兆円を突破。一定の成長率を前提にした場合でも、同じ年度末の発行残高は899兆6千億円に膨らむとしている。 |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.82 | 2003/2/12(水) 日本経済新聞より |
資産再生へのシナリオ 不動産に証券化取引を主体にした新しい市場が登場し、規模が拡大している。REIT(不動産投資信託)がその代表例で、利回りとリスクを査定し、価格が決められるため、金融商品としての比較が可能になった。これにより、不良債権処理や、実施が決まった減損会計導入による企業の不動産対策も容易になり、不動産証券化取引に関連するビジネスが急成長している。 失われた「国富」の回復へ 不動産取引の価格公開が鍵 不動産証券化が急拡大 ”旧市場”は需要不足で低迷 内閣府の国民経済計算によると、日本の土地資産は、ピーク時と比較し約一千兆円が失われた。バブル前の1986年の水準に戻りつつあるという。2001年末時点で日本の土地の時価総額は1455兆円(国民経済計算)で、名目国内生産(GDP)の約3倍。約5倍に達したバブル期に比べてかなり下がったとはいえ、米国の0.9倍、英国の1倍と比べるとなお高いため、地価の調整は終わっていないとの指摘は以前多い。 問題は、デフレ対策といっても、マクロ的政策をいくら打っても、不動産に関する限りミクロ的な対策抜きには効果がないことである。 現在、わが国不動産市場は、「ダブル市場」となっている。バブル市場のメカニズムを色濃く残す下落の止まらない市場と、そことは全く異なる市場構造を持つ新興勢力のマーケットが同時に存在する。 区別のために前者を旧市場、後者を新市場と呼ぶ。 旧市場では、そのインフレ価格の虚構性にわが国経済が気づくとともに、価格への信頼が崩壊し、過度の不振に陥り、その心理的な要因が強力なファクターとして支配しているのが特徴だ。 「デフレスパイラル的下落」や、「価格不信」は旧市場に限っての現象であることに注意しなければならない。 通常、地価は金利や賃料の変化を受け、アップダウンする。金利が下がれば地価は上昇する。ところがこの旧市場下では、価格下落や低金利と、投資に最適な経済環境にもかかわらず需要不足で、地価は11年間、一方的に下がり続けるという異常現象が生じている。 対して、新市場は旧市場とはまったく異なる構造をなす新しい市場で、この数年に誕生し、急成長している。 DCF法で利回り・リスク評価 金融商品間の比較可能に 両者の最大の違いは、間接金融が支配的であった旧市場に対し、新市場では直接金融が中心となっていることだ。旧市場が金融機関による不動産と担保主義と相対取引を主流とする実物取引を特徴とし、高額取引が可能な主体に限って不動産投資が可能であったのに対して、新市場はREITに代表される不動産証券化取引を中心とした、投資金額の少額性と投資家の大衆・一般化を特徴とする。 資源配分の側面から見ると、旧市場から新市場への転換とは、わが国不動産が、かつての限られた所有者から離れ、それぞれの価値に応じた新しい利用者、使用者へとシフトしているといえよう。 また価格も大きく違う。旧市場では公示地価、路線価がベースとなっている。この市場では公共事業の用地買収が、高止まり傾向の公示価格をベースとして行われるため、それが旧市場価格水準を下支えする構造を持つ。 一方、新市場ではDCF(割引現在価値)収益価格が一般的である。この価格は、不動産が生み出すキャッシュフローに着目してそれを割引き率で現在価値に割り引いて求める。この評価手法をDCF法と言う。割引率は、一般的な金利水準と、個別のリスクから構成される。 DCF評価では利回り(リターン)とリスクの査定なしには価格が成立しない。よって投資家は、それらを判断基準としてほかの金融商品との比較が可能となる。種々のリスクを盛り込めるので、欧米でもリスクに適応した評価法として、認識されている。また、DCF価格取引が米国のように一般化することは、不動産の稼動性や収益構造が吟味されることを意味する。 不動産は働かせる時代 テナント構造の見直しなどを 保有しているだけで価格が成立していた「古きよき時代」は終わった。これからは不動産はきちんと働かせる時代である。テナント構造を見直し、財務状況のよいテナントと入れ替え、また賃料水準が適正か、維持管理費に無駄はないかなど、不動産を再生させることから始めねばならない。 本来、価格は、相互に反応し合い次第に均衡していくはずであるが、わが国ではその動きは見られず新旧市場それぞれでダブルスタンダード化、むしろ対立構造となっている。 よって、わが国不動産における資産デフレ対策は、旧市場をどうするかである。低金利政策や財政出動は、一般的なデフレに有効でも、旧市場の価格不信からくる需要不足にはまったく効かない。唯一の処方せんは価格メカニズムの回復である。 それにはまず、日本中の不動産取引の価格を公開することだ。登記簿への記載を義務化すれば済む。コストがほとんど不要でかつ最大効果を発揮する構造改革である。市場健全化のため最初にすべきインフラ整備である。 この情報流通があれば、マーケット自身で価格が適正かどうかを判断する物差しをもてることとなり、価格や需要の動向もつかめ、投資判断が可能となる。こうして価格が本来の機能を取り戻せるし、ダブルスタンダードも解消へ向かう。 価格機能の回復なしには、いつまでも「底打ち」がマーケットに認識できない。底打ちをマーケット自身が判断すれば、必ず価格が反転する。それがさらにより多くの投資家をひきつけ、価格がさらに上昇していくという好循環が生まれる。 日本経済再生はここから始まる。 〈都市経済研究所代表取締役 久恒 新〉 |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.81 | 2003/2/11(火) 南日本新聞より |
デフレ懸念 世界に広がる 主要中央銀 阻止へ 対インフレから転換 各国とも政策に急所 世界各国でデフレ懸念が広がり、主要国の中央銀行が日本を教訓に、水際でデフレを阻止しようと政策の軸足をシフトし始めた。インフレ抑制を最大課題としてきた各国中銀は、これまでとは正反対の「デフレファイター」に変身できるのか。ジレンマを抱え試行錯誤する米欧や中国の取り組みを探った。 米連邦準備制度理事会(FRB) のバーナンキ理事は昨年末、「日本は政策対応が遅く不十分だったためデフレが長期化している」と指摘。国内のデフレ懸念には「予防的に行動する」と政策当局として迅速な対応をとる決意を示した。 昨年11月の0.5%もの大幅利下げはその証だ。グリーンスパン議長は「フェデラルファンド(FF)金利がゼロに近づけば政策余地がなくなるとの見方は間違いだ」として量的緩和も辞さない方針を示し、対デフレへの強い姿勢を鮮明にした。 ドル安は禁じ手 米国は昨年12月の卸売物価指数が過去最大の下げ幅を記録した。中国製など安い輸入品の増加で国産品への値下げ圧力が強まっているためだ。産業界はドル安を求めるが、ブッシュ政権はドル高維持の立場。ドル安はデフレ圧力の緩和につながる半面、日欧から集まった投資マネーの流出を招き、巨額の経常赤字のやり繰りができなくなって株価暴落を誘発しかねないジレンマがある。 FRBと政府の景況感は微妙に異なるが、いったんデフレに陥れば現状の政策手段では脱出が難しいという点では一致する。このため、政策当局は早めの金融緩和と大幅減税などの需要喚起策で事前にデフレの芽を摘むことを重視している。 対インフレから転換 各国とも政策に急所 欧州中央銀行(ECB)も昨年12月、政策金利を0.5%引き下げた。ユーロ圏経済のけん引役ドイツの実質経済成長率は前年比0.2%と1993年以来の低成長。個人消費や設備投資の低迷、政府支出の大幅削減で物価下落圧力は一段と強まりつつあリ、デフレの影が忍び寄る。 問題は経済状況が異なる域内各国に共通の金融政策が適用されること。ECBはユーロ圏12カ国平均のインフレ率を判断基準として金融政策を決定する。加盟国中でデフレ色が濃いドイツにとって金融緩和のタイミングが遅れがちとなることが最大の悩みだ。 中国はインフレへ依存 中国人民銀行も昨年末に戴相龍総裁(当事)が「ここ数年、金融政策の重点はデフレ防止だった」と述べるなど、地方工場からの安い製品が都市部のデフレを招く事態を重視してきた。公共事業を中心とした需要創出のため今年も1400億元(約2兆1千億円)の国債を発行する。ただ、活発な不動産投資が引き起こす資産インフレも並存し、当局は両面対応を強いられている。 「中国デフレ輸出論」を背景とした日本などからの人民元切り上げ要請については「デフレは自国の不景気が主因」(中国社会科学院経済研究所の袁鋼明主任)と反論に躍起だ。 (ワシントン、北京、ベルリン共同) |
|
トップページ
目次へ戻る
| NO.80 | 2003/2/3(月) 日本経済新聞より |
エコノミクスNOW 伊藤元重 東大教授 都市集積が新産業育てる サービス化の基盤 規制改革で市場に推進力 都市には集中と発散という二つの力が働いている。最近、東京都心で集中がより強く働いていることは、規模の経済性を生み、サービス産業化のための新たなビジネス機会や雇用を生む効果がある。 最近の東京都心の変ぼうぶりには目を見張るものがある。品川や汐留の再開発、新丸ビルを起点とした丸の内地域の商業集積の集中、4月に予定されている森ビルの六本木ヒルズのオープン。次々に立つ高層ビルによって、東京都心の風景はすっかり変わってしまった。 今年は特に都心部における建設ラッシュで、マスコミはオフィススペースの過剰供給を心配して2003年問題という名称までつけている。都心部の開発が進んでいくことは、新たなビジネスチャンスや雇用機会を生み出すものであるので2003年は都市活性化飛躍の年と言うべきである。「2003年問題」と悲観的にとらえるところに、すべての現象を悲観的に見たがる現在の日本の世相が反映されている。 ともあれ、都心部が、再開発されていくことは好ましいことである。こうした現象が最近とみに顕著になっている背景にはどのような経済メカニズムが働いているのか、そしてそうした変化は日本経済にどのような影響を及ぼしうるのか検討する必要がある。 「集中」「発散」二つの力働く 都市構造形成に関する経済モデルには多様なものがあるが、その多くが中心部(center)への集中と周辺(periphery)への発散の二つの力の存在を指摘している。「中心部」には東京や大阪のような都市の中心部という意味と、日本における東京のような中心的な都市という意味が込められ、「周辺部」には都市の郊外という意味と地方都市という意味が込められている。都市の構造は都市の中心へ集まる力と郊外に発散する力のバランスの上で形成される。そして、国土利用の構造は大都市への集中と地方への発散の力のバランスの上で決まってくる。 都市の構造の変化においては一貫して中心への集中の力が働いていると考えられがちだ。しかしその背後には常に集中と発散という二つの相反する力のバランスがあることを認識する必要がある。東京のような大都市を例にとれば、バブルの時代には郊外に向かった発散の力が働いた。だからこそ郊外化の現象が顕著であったのだ。最近都心回帰の傾向が見られるのは、中心に向かう力が働くようになっているからだろう。 なぜ、最近中心への力がより強く働くようになっているのだろうか。様々な要因が考えられる。たとえば、高層ビルを建設する技術が格段に進歩したことは重要な要因だろう。東京に高層ビルが次々に立っていることは、こうした技術の変化をうかがわせる。ただ、こうした技術的な要因以上に重要であると考えられるのが、産業構造の変化である。農業から工業、そして工業からサービス産業へと産業の重点が変化していけば、それにともなって都市の姿が変わるのは当然のことである。 ほんの50年ほど前まで、日本は農業中心の社会であった。農業は大地の上で行う産業活動である。当然、日本の人口は全国に散らばることになる。この時代には中心への集中への力はあまり強くなかった。最近、全国で市町村合併を進めようとする動きがやっと出てきた。これは、かつての農業社会の時代の地域経済を反映した、時代錯誤とも言うべき細かすぎる行政区域を、なんとか経済活動や生活実態にあったものにしようとする動きという面を持っている。 地域に規模の経済性を生む 高度経済成長期に入って、日本の産業は急速に工業化の道を歩んだ。それに合わせて、人口の移動が起きたのだ。土地から開放された工業労働者は、大都市近郊に移り住んだ。そして、太平洋ベルト地帯を中心に日本経済の都市化が進展していった。ただ、工業社会の都市の構造は、工場での生産を支える生活の場としての都市に過ぎない。モノを生産する工業地域は、住宅地域とは分離されることになるし、大都市ではより広い住宅を求めて郊外化が進むことになる。大都市近郊で次々に作られたニュータウンは、こうした動きのなかの一つの現象である。 現在、日本の産業構造は明らかにサービス化の度合いを強めている。ここでサービス化とは、金融・医療・教育・エンターティンメントなど産業分類上第3次産業に分類される産業の比重が大きくなるということだけのことではない。製造業に分類される企業でも、企業活動の多くの部分がデザイン・研究活動・設計・広告・マーケティングなど、サービス産業的な活動となっている。サービス型の産業の特徴は、単独では存立できないことだ。他の企業、顧客、政府や研究機関など、社会のあらゆる部分と濃密なネットワークがあって、はじめて存立できる場合が少なくない。 これは、工場という独立した空間の中で基本的な活動を行うことができる工業とは異なる。工業においても部品産業や下請けなどのネットワークの存在は重要である。だからこそ、産地の集積が形成される。しかし、しょせんそれはモノの流れを中心としたネットワークにすぎない。これに対して、サービス産業にはより多様なネットワークの存在が必要となる。 現在の都市は職住遊学などが混在したものでなくてはいけないと言われる。よい人材を集めるには近くによい住宅が必要であり、企業活動は大学などの研究機関のサポートが必要になる。また、楽しい町でないと住宅地やオフィス街の魅力も薄れる。こうした背景には、産業活動だけでなく、生活・レジャー・研究・教育など、多様な活動が相互に複雑な外部効果を持っていることがある。 経済学ではこうした現象を集積効果と呼んでいる。集積効果によって地域全体に規模の経済性が生まれる。その規模の経済性のダイナミズムを理解することなく産業の発展を議論することはできないのである。これは、サービス産業の比重が大きくなった現代社会に特に強く見られる現象なのである。 比ゆ的な言い方だが、工業化の時代には「産業が都市を育てる」という面が強かった。工場を誘致してくることがその地域の活性化につながったのだ。しかし現代においては「地域が産業を育てる」という面のほうが強くなっている。高度な集積を抱えた元気な町にはよい人材が集まり、よい企業が育つのである。 金融の中心であるロンドンやニューヨーク、ファッションのパリやミラノ、エンターティンメントのロサンゼルス、ハイテクのボストンやシリコンバレーなど都市内の集積が産業の発展の原動力となっている。そして、そうした高度な集積を持った都市を抱えることがその国の経済力の向上につながるのだ。 世界は都市間競争の時代に 都市への集積が産業発展の原動力となっていることは、世界的な現象である。世界は都市間競争の時代に入っており、強い都市を抱えている国はその恩恵を強く受けることになる。日本の産業の活性化を推進する上で、都市政策が非常に重要であることは明らかだ。 大阪が東京に比べて元気がない理由はいろいろあるだろうが、かつて多くの大学を郊外に移転させてしまったこともその理由の一つだろう。将来を支える有能な若者が都心部に少ししかいない町を活性化させることは難しい。東京も多くの課題を抱えている。アクセスのよい国際空港の不在、道路インフラの不整備による慢性的な渋滞などは、集積としての東京の魅力を弱めている。 インフラを是正するには時間がかかるだろう。しかし、民間の活力を利用して都市の改造をしていくことはできるはずだ。今、東京都心で起きている建設ラッシュは、都市改造を推進しようとする市場メカニズムのパワーそのものなのである。そして、そうした市場メカニズムを活性化させるためにも、都市再生に焦点を当てた規制緩和が必要なのである。 最後に一つ事例を挙げておこう。東京駅の再開発のプロジェクトが計画されている。古い駅舎を残すため、その部分には高いビルを建てないそうだ。その結果生じた空中権を他の開発主体に売ることで、東京駅の再開発のために潤沢な資金を集めることができる。空中権の売買に関する規制緩和によって、空中を利用しない東京駅の開発も、空中権をより大きく利用したい隣接地域の開発も推進される結果になったのだ。都市改造を進める上での規制改革の重要性を示したよい例である。 |
|
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.79 | 2003/1/31(金) 日本経済新聞より |
購買力 広州が最大 中国3大都市 上海・北京上回る 北京、上海、広州の中国三大都市のうち、広州市民の購買力が最も大きいことが明らかになった。各市の2002年統計によると、広州市民の一人当たりの年間平均可処分所得は13380元(約20万円 一元=約15円)と、上海や北京を上回った。 一人当たりの年間支出額も広州が10672元と両都市より多く、一人当たり域内総生産(GDP)も3都市の中で始めて5000ドルを超えた。外資系企業の多くは従来、華南を輸出加工基地と位置付けてきたが、「上海と肩を並べる消費市場」(三菱商事)としても見直されつつある。珠江デルタ地帯には一人当たりGDPが3000から5000ドルの都市が密集。日米欧の流通大手が出店攻勢をかけている。 (広州=北代望) |
|
トップページ
目次へ戻る
.
トップページ
目次へ戻る
.
| NO.77 | 2003/1/15(水) 日本経済新聞より |
技術・ブランド強み コマツ全利益の4割 ホンダ2ケタ増益 中国事業を収益源にする日本企業が増えてきた。コマツは全社利益の4割を中国で計上し、ホンダの現地法人も二ケタ増益を達成した。ブランド力や技術力のある企業は競争の激化する消費財でも利益を出し始めている。日米欧市場の成長鈍化が鮮明になるなかで今後、中国を含めたアジアに収益の軸足を移す企業が増えるのは確実。日本経済に与えるアジアの影響も増しそうだ。 生産財 コマツが1995年に設立した中国の現地生産法人「小松山推」は2003年3月期、税引き前利益が円換算で49億円と前期比63%増える見通しだ。単純計算でコマツの今期予想連結税引き前利益の約4割を占める。 コマツは高い技術力を売り物に中国市場に参入し、独自の販売ルートを開拓。2008年の北京五輪を控え、主力の油圧ショベルの市場規模は年間約7割増のペースで拡大している。「日本メーカーの製品力が受け入れられている」(コマツの板垣正弘社長)という。 工作機械でもファナックは、2002年9月中間期の持分法投資利益が前年同期比75%増え16億円に。増加分の約3割は中国の現地法人が稼いだと見られる。他メーカーも中国事業を強化、国内工作機械メーカーの中国を含めたアジアからの受注額は、2002年に年間で初めて北米を上回ったもようだ。 消費財 中国を収益源にし始めた日本企業は、ブランド力のある消費財メーカーにも広がりつつある。 「アコード」などを生産するホンダの中国現地法人、広州本田汽車の2002年12月期は売上高が前の期比13%増の約二千億円、税引き前利益は12%増の約750億円になったもようだ。昨年の生産台数は5万9千台と16%増えた。 広州本田は1998年の設立でホンダは50%を出資。ホンダの持分法投資利益は2003年3月期に前期比32%増の560億円程度になる見通しで、うち約半分を中国で稼ぐ。持分法利益を含んだ純利益は今期過去最高を見込む。 自動車ではブランド力のあるホンダ、トヨタ自動車、日産自動車の中国現地生産の規模が現在の年10万台程度から5年後には一気に100万台程度に膨らむと見られている。 電機ではパナソニックブランドが浸透してきた松下電器産業の中国国内での販売額と中国から他地域への輸出額を合わせた売り上げ高が、2002年(1から12月)は前年の1.5倍の約4500億円に拡大。2005年には1兆円にほぼ倍増させる計画で営業利益でも1千億円を目指す。 日本企業は従来、中国を主にコストの安い生産拠点として活用してきたが、収益源としての重みが急速に高まっている。現地企業との競合などで苦戦する日本企業は依然として多いが、市場としての中国をいかに攻略するかが業績を左右する局面に入ったといえる。 中国で利益を伸ばす主な企業 ▽コマツ 現地生産法人の税前利益は03年3月期に63%増の49億円。 主力の油圧ショベルで市場を開拓 ▽ファナック 02年9月中間期の持分法投資利益の増加分の約3割が中国。 コンピューター数値制御システムでシェア約5割 ▽ホンダ 広州本田の四輪車が好調。02年12月期の税前利益が750億円。 持分法投資利益の約半分を中国で稼ぐ ▽資生堂 中国専用ブランドを販売。 中国での売上高は03年3月期3割増の170億円。 96年から黒字続く ▽キューピー 中国でのマヨネーズのシェア1位。 北京の現地法人の02年12月期売上高は12%増の9億円 黒字定着 |
|
トップページ
目次へ戻る
.