| NO.70 | 2002/12/6(金) 日本経済新聞より |
デフレが蝕む データ編③ 土地資産 ピーク比965兆円減 GDPの3倍、なお割高の見方も |
|
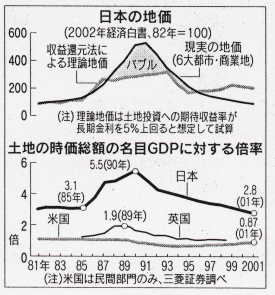 |
|
| 国の損益計算書や貸借対照表に当る内閣府の国民経済計算によると、日本の土地資産はバブル崩壊後の1990年末をピークに減り続け、2000年末までに965兆円の資産価値が失われた。地価はバブル前の80年代半ばの水準に戻った。 資産デフレに照準を合わせた今年の経済財政白書は、土地から見込める収益に基づいて現在価格を割り出す「収益還元法」に基づく分析をしている。(グラフ参照) 六大都市の商業地の場合、1996年に収益還元法に基づく理論価値と同水準まで現実の地価が下落。その後は理論価値を下回る状態が続いているという。地価下落に弾みがつき、下げ過ぎにつながったというわけだ。「土地はそろそろ下げ止まり」との主張はこうしたデータに根拠がある。 だが、地価の調整は終わっていないとの指摘は依然多い。昨年末時点で日本の土地の時価総額は1444兆円(三菱証券推計)で、名目国内総生産(GDP)の約3倍。約5倍に達したバブル期に比べてかなり下がったとはいえ、米国の0.9倍、英国の1倍と比べるとなお高い。 三菱証券の水野和夫チーフエコノミストは「工場の海外移転が続くうえ数年後に人口が減少に転じる。需要の減少に伴う地価下落は長期化する」と予測している。商業地に比べ下げが緩慢な住宅地には一段の下げ余地があるとの指摘もある。 白書は利便性による地価の2極化も指摘している。以前は周辺の取引価格に合わせてほぼ決まっていた地価が立地条件などによって明確に差がつくようになったとしている。 結果的に地価は地域の経済力との連動性が強まっている。今年の公示地価のうち商業地の地価を見ると、東京圏は前年に比べて下げ渋る一方、地方は大幅に下がった。同じ東京都千代田区内でも、もともと地価が高く好立地の場所は収益期待で値段が上昇に転じたところもあるのに対し、相対的に不便な地点は二ケタの下落が続いた。 |
|

